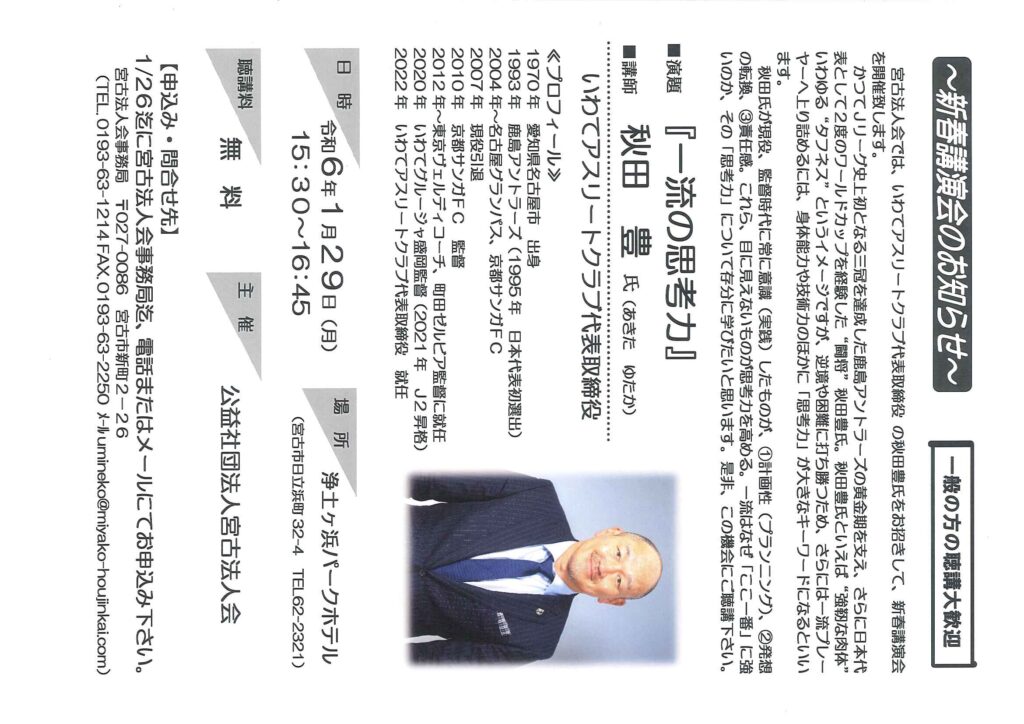総務省は2023年の全国消費者物価指数は前年比3.1%上昇の105.2となったと発表した。第2次石油危機が影響した1982年以来41年ぶりとなる大きな伸びとなった。消費者物価指数の上昇は2年連続。2023年平均を項目別にみると、生鮮食品を除く食料が前年比8.2%上昇となり、1975年以来48年ぶりの高さとなっている。原材料費や輸送費の上昇分が価格に転嫁されたことが背景にある。家計への負担が増していることを浮き彫りにしている。
国際通貨基金(IMF)は人工知能(AI)の普及で世界の雇用の約40%が影響を受けるとの見通しを明らかにした。IMFは専門職などの知的労働者が多い先進国では雇用の約60%がAI普及で影響を受けるとしている。IMFは「中程度のスキルの労働者が最も打撃を受けた自動化の普及と異なり、AIよる失職リスクは高所得者に及ぶ」と指摘するとともに、失職などで経済格差を拡大させる恐れがあるとしている。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は1月20日、小型月着陸実証機SLIM(スリム)が月面着陸に成功したと発表した。日本の月面着陸は、旧ソ連、米国、中国、インドに続き、世界5カ国目となる。また、月面着陸の直前に、搭載した2代の小型ロボット「LEV-1」「LEV-2」の分離にも成功している。SLIMは昨年9月に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、12月には月の周回軌道に入り、20日午前0時頃から月面へ約20分をかけて降り立った。
1月19日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価(30種)の終値が3万7863.80ドルとなり、史上最高値を更新した。背景には米ミシガン大が発表した1年先のインフレ予想(物価上昇)率が約3年半ぶりに低水準となったことで、インフレ収束への期待が高まったことから株式が買われ、株価を押し上げた。ダウ平均は米連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測が強まったことから、昨秋から上昇傾向にあった。
観光庁の発表によると、2023年に日本を訪れた外国人の消費額は5兆2923億円となり、2010年の統計開始後、初めて5兆円を超えたことが明らかになった。1人当たりの平均消費額は21万2千円となっている。消費額を国・地域別にみると、台湾が7786億円で最も多く、中国(7599億円)、韓国(7444億円)、米国(6062億円)が続いた。2023年の訪日客は推計2506万人で、コロナ禍前の2019年の約8割まで回復している。
東京商工リサーチは2023年の企業倒産は前年比35.2%増の8690件になったと発表した。増加は2年連続で、2019年以来8千件を超え、増加率はバブル崩壊後の1992年以来31年ぶりの高さとなった。増加している背景には、新型コロナウイルス対策の実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の本格返済で資金繰りの重圧に加え、原材料価格の高騰、人手不足による人件費上昇圧力が経営を圧迫したことが挙げられている。同社では「2024年の企業倒産が1万件を超える可能性が出てきた」としている。
総務省のまとめによると、2022年度の地方公務員の採用試験の倍率は5.2倍となり、過去30年間で最も低かったことが明らかになった。対象は全国の都道府県、政令指定都市、市区町村の事務職・技術職などの職員で、教員は含まれていない。採用試験の受験者が最低となった背景には、少子化の状況に加え、待遇などへの不満から受験者が減ったことが要因とみられている。就職氷河期世代が新卒だった1999年度は14.9倍で、3分の1にとどまっている。
調査会社クロス・マーケティングが20~79歳の男女を対象に直近1カ月間の目の疲労度を尋ねたところ、「よく疲れている」(28.5%)、「たまに疲れている」(40.7%)と答え、7割近くが目の疲労度を感じていることが分かった。年代別に目の疲労度をみると、50代が76.0%で最多だった。また、スマートフォンの1日の利用度が長い人ほど「よく目が疲れている」と答えていることが分かった。